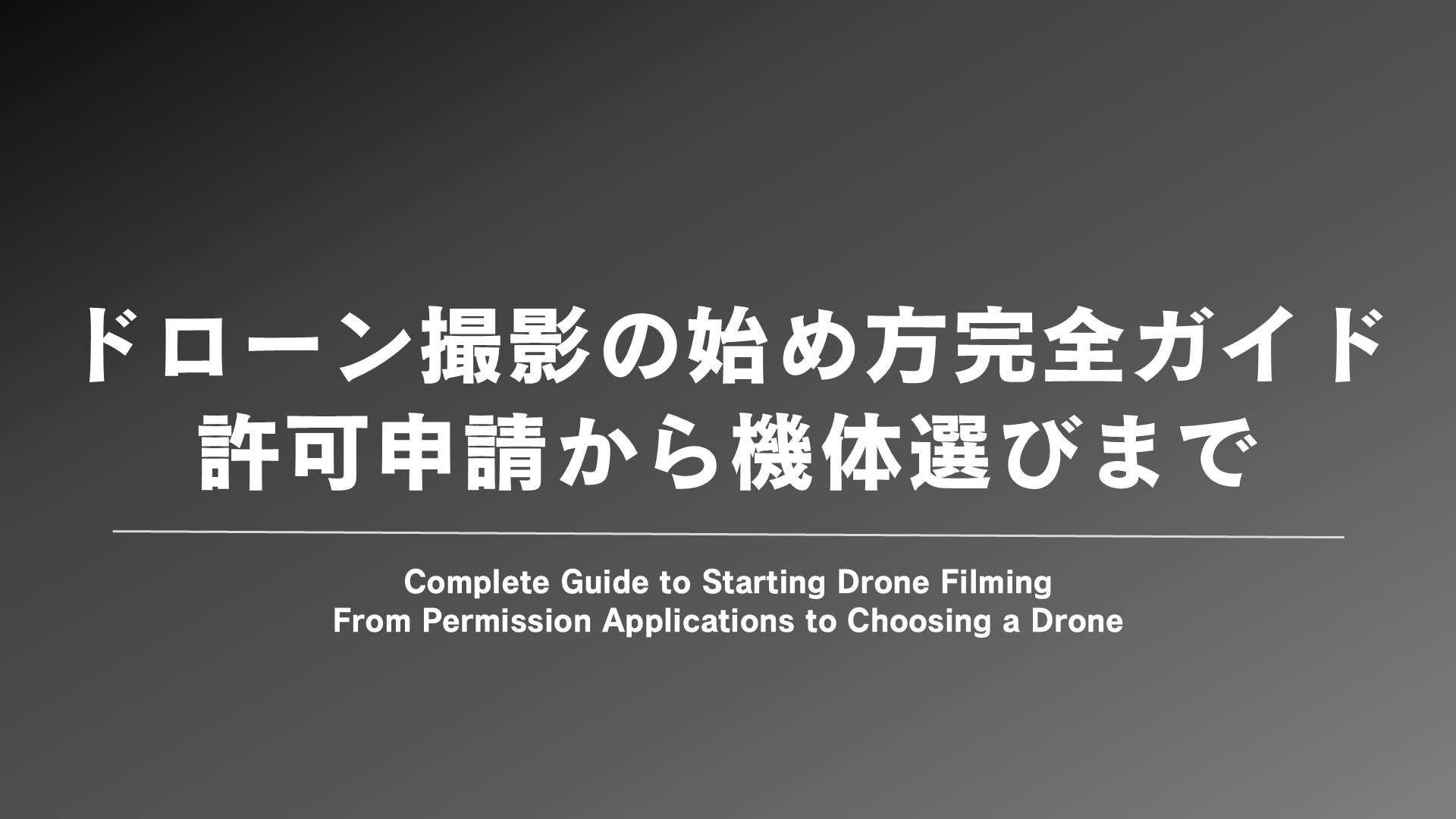
「まるで鳥になったような視点から、息をのむ絶景を撮影してみたい」
「自社の物件やイベントを、ダイナミックな映像でPRしたい」
SNSやテレビで目にするドローンを使った空撮映像は、私たちの心を惹きつけます。
しかし、いざ自分でドローン撮影を始めようとすると、「法律が厳しそう…」「許可申請ってどうやるの?」「どのドローンを選べばいいか分からない」といった不安や疑問が次々と湧いてくるのではないでしょうか。
ご安心ください。この記事では、ドローン撮影に興味を持ち始めた初心者のあなたのために、必要な法律の知識から許可申請の方法、おすすめの機体選び、そして魅力的な映像を撮るテクニックまで、知りたい情報をすべて網羅しました。
この記事を最後まで読めば、安全かつ合法的にドローン撮影を始めるための具体的なステップがすべて分かります。
さあ、一緒に空撮の世界への第一歩を踏み出しましょう。
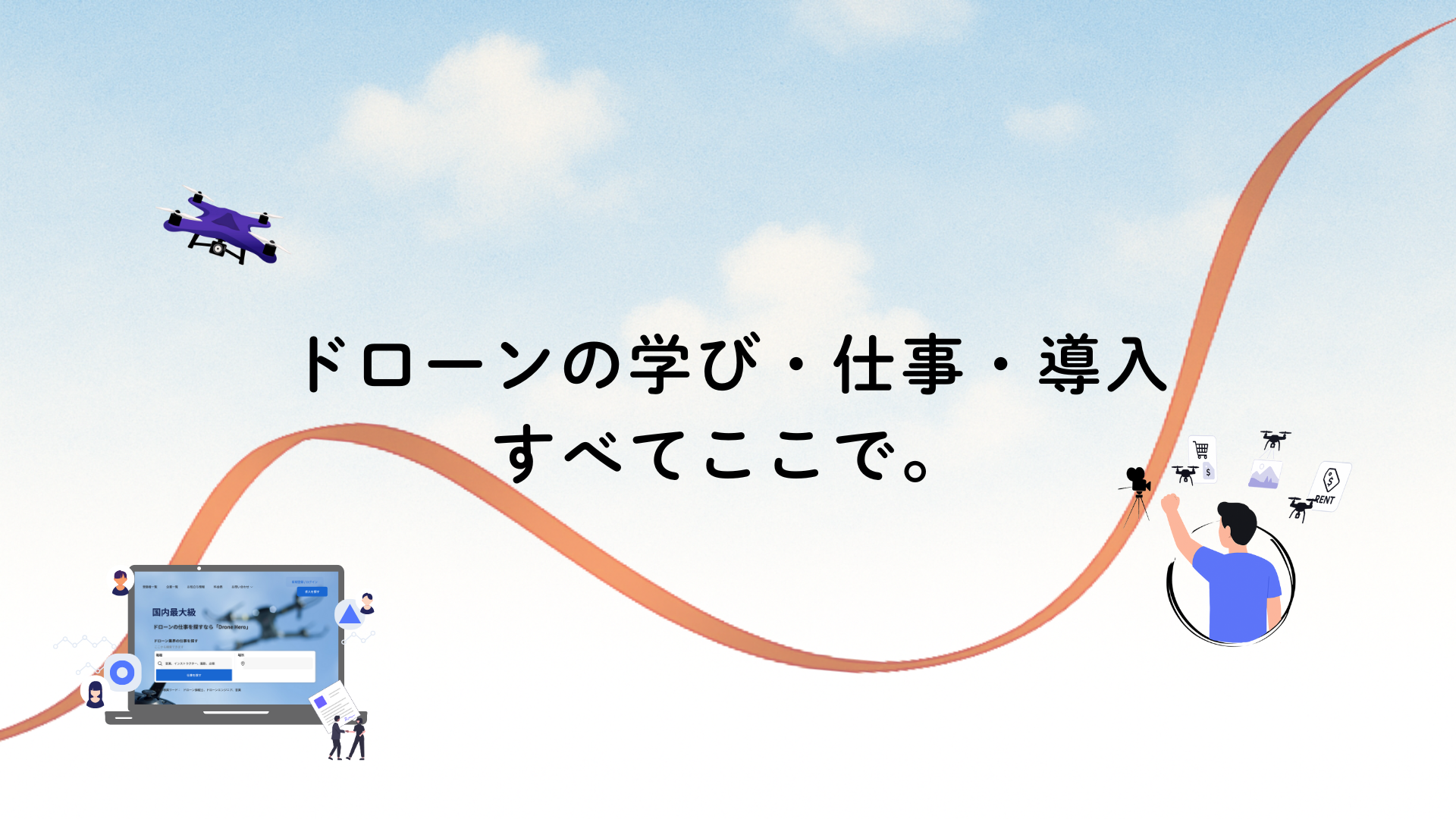
ドローン撮影のルールと許可申請
ドローン撮影を始める上で、最も重要で、最初に理解すべきなのが法律やルールです。安全な飛行のため、そして知らずに法律違反をしてしまうことを防ぐため、以下のポイントをしっかり押さえましょう。
100g以上の機体は登録が義務

まず知っておくべきなのは、重量100g以上のすべてのドローンは、国への機体登録が法律で義務付けられているという点です。
登録された機体には、人間でいうマイナンバーのような識別情報を電波で発信する「リモートID(ドローンの機体情報を遠隔で識別するための機能)」の搭載が原則として必要になります。これにより、空の安全が管理されています。
機体の登録は、国土交通省の「ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)」からオンラインで行えます。
(参考:無人航空機登録ポータルサイト)
飛行許可が必要な空域(人口集中地区など)
ドローンはどこでも自由に飛ばせるわけではありません。
航空法により、以下の特定の空域でドローンを飛行させる場合は、事前に国土交通大臣の許可が必要です。
- 空港等の周辺: 進入表面等の上空の空域。空港によって範囲が異なるため、国土地理院の「地理院地図」などで確認が必要です。
- 緊急用務空域: 警察や消防などが救助活動のために設定する空域です。国土交通省のウェブサイトやX(旧Twitter)で公示されます。
- 150m以上の高さの空域: 地表または水面から150m以上の高さで飛行させる場合は許可が必要です。
- 人口集中地区(DID)の上空: 国勢調査の結果に基づいて設定される、人口密度が高い地域です。都市部のほとんどが該当するため、飛行前には必ず「SORAPASS」 や「地理院地図」で確認しましょう。

飛行承認が必要な方法(夜間・目視外飛行など)
特定の空域だけでなく、飛行方法によっては国土交通大臣の承認が必要になります。空撮で使いたいテクニックが該当する場合も多いので、しっかり確認しましょう。
- 夜間飛行: 日の入りから日の出までの時間帯に飛行させる場合。
- 目視外飛行: ドローン本体を操縦者の肉眼で見えない範囲で飛行させる場合(FPVゴーグルを使った操縦も含む)。
- 人または物件との距離30m未満の飛行: 第三者やその所有物(建物、車など)との間に30m以上の距離を保てない飛行。都市部での撮影ではほとんどの場合で該当します。
- イベント上空飛行: お祭りやコンサートなど、多数の人が集まる催しの上空を飛行させる場合。
- 危険物輸送: 農薬や医薬品など、危険物を輸送する場合。
- 物件投下: ドローンから物を投下する場合(農薬散布や物資輸送など)。
許可不要でドローンを飛ばせる条件
「じゃあ、許可なしでドローンを飛ばすのは無理なの?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。以下の条件を満たせば、許可・承認なしでドローンを飛ばすことが可能です。
- 重量100g未満のドローンを飛ばす場合: 100g未満の機体は航空法の規制対象外となる部分が多いため、上記の飛行許可・承認は不要です。(ただし、空港周辺や緊急用務空域の飛行禁止、飲酒操縦の禁止などのルールは適用されます)
- 許可・承認が不要な場所・方法で飛ばす場合: 100g以上の機体でも、前述した「許可が必要な空域」と「承認が必要な方法」のいずれにも該当しないのであれば、許可・承認は不要です。
- 屋内で飛行させる場合: 体育館や倉庫、自宅の部屋の中など、完全に屋内であれば航空法の適用外となり、自由に飛行させられます。
- 四方をネットで囲まれた場所で飛行させる場合: ドローン練習場など、側面と上面がネットで囲われている施設も航空法の適用外です。
初心者のうちは、まず許可のいらない場所で練習を積むのがおすすめです。
国土交通省へのオンライン申請(DIPS)手順

飛行許可・承認が必要になった場合、申請は「ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)」を通じてオンラインで行うのが一般的です。
- アカウント開設: DIPS 2.0の公式サイトで、個人または法人のアカウントを作成します。
- 操縦者・機体情報の登録: 操縦者情報(住所、氏名など)と、所有するドローンの情報(製造者、型番など)を登録します。
- 飛行許可・承認申請書の作成: 飛行日時、場所、目的、飛行方法などを入力し、申請書を作成します。
- 申請書の提出: 作成した申請書をオンラインで提出します。審査には通常、数日~2週間程度かかります。
計画的に、余裕をもって申請を行うことが重要です。
(参考:国土交通省 ドローン情報基盤システム DIPS 2.0)
ドローン撮影に役立つ資格の種類
「ドローンを飛ばすのに資格は必須ですか?」という質問をよく受けますが、趣味の範囲で飛ばすだけであれば、資格は必須ではありません。
しかし、ドローンの資格を取得すると、以下のようなメリットがあります。
- 知識と技能の証明になる
- DIPSでの許可・承認申請の一部を簡略化できる
- クライアントからの信頼を得やすくなる
ドローンの資格には、国が定めた「国家資格」と、民間のスクールが発行する「民間資格」があります。
- 国家資格(無人航空機操縦者技能証明): 「一等」と「二等」があり、特に一等資格は、有人地帯での目視外飛行(レベル4飛行)など、特定の高度な飛行を行うために必須となります。
- 民間資格: DJI CAMPやJUIDA、DPAなどが有名です。基礎的な知識と操縦技術を体系的に学ぶことができ、初心者にはおすすめです。
初心者向け撮影用ドローンの選び方
ルールを理解したら、次はいよいよ相棒となるドローン選びです。しかし、数多くの機種の中から自分に合った一台を見つけるのは大変ですよね。ここでは、初心者の方が撮影用ドローンを選ぶ際に重視すべきポイントを解説します。
選ぶ際の重要ポイント5つ(画質・安定性・価格)
- 画質(解像度・センサーサイズ): 美しい空撮映像を撮るなら、最低でもフルHD(1920×1080)、できれば4K(3840×2160)の解像度で撮影できるモデルを選びましょう。また、光を捉える「イメージセンサー」のサイズが大きいほど、暗い場所でもノイズの少ない綺麗な映像が撮れます。
- 飛行安定性(GPS・センサー): 初心者にとって最も重要なのが飛行の安定性です。GPSを搭載したモデルは、風に流されても自動で位置を維持してくれます。また、障害物検知センサーがあれば、衝突のリスクを減らせるため、安心して操縦に集中できます。
- 飛行時間(バッテリー): ドローンの飛行時間は、1つのバッテリーで20分~40分程度が一般的です。しかし、離陸から撮影ポイントへの移動、撮影、着陸までを考えると、実際の撮影時間はもっと短くなります。予備のバッテリーを2~3本用意しておくのがおすすめです。
- 重量: 前述の通り、100gを境に法律の規制内容が変わります。100g未満のモデルは手軽ですが、風に弱く画質も劣る傾向があります。本格的な空撮を目指すなら、安定性に優れた100g以上のモデルがおすすめです。
- 価格: 撮影用ドローンの価格はピンキリです。初心者の場合、まずは5万円~15万円程度の価格帯から検討するのが良いでしょう。この価格帯には、十分な画質と飛行安定性を備えたコストパフォーマンスの高いモデルが揃っています。※いきなり購入するのではなく、「レンタルを推奨します」。困ったらTacticsまで相談してください!
価格帯別おすすめドローンモデル比較表
| 価格帯 | モデル名 | 解像度 | 飛行時間 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 5~10万円 | DJI Mini 3 | 4K/30fps | 38分 | 縦向き撮影に対応。SNS向けの動画撮影に強い。 |
| 10~15万円 | DJI Mini 4 Pro | 4K/60fps | 34分 | 全方向障害物検知を搭載。安全性と高画質を両立。 |
| 15万円以上 | DJI Air 3 | 4K/60fps | 46分 | 広角と中望遠のデュアルカメラ搭載。表現の幅が広がる。 |
※価格やスペックは変動する可能性があるため、最新の情報は公式サイトでご確認ください。
目的別(趣味・仕事)のおすすめ機種紹介
趣味・旅行での空撮を楽しみたいなら
DJI Miniシリーズ(Mini 3, Mini 4 Proなど)がおすすめです。249gと軽量で持ち運びやすく、カバンに入れて気軽に旅行へ持っていけます。それでいて4K撮影に対応し、飛行安定性も抜群。「手軽だけど、映像のクオリティには妥協したくない」という方にぴったりです。
本格的な映像制作や仕事で使いたいなら
DJI Airシリーズ(Air 3など)やMavicシリーズが選択肢になります。より大きなイメージセンサーや高性能なカメラを搭載し、プロレベルの映像品質を実現します。特にDJI Air 3は、広角と中望遠の2つのカメラを切り替えることで、多彩な映像表現が可能です。

ドローン撮影の始め方5ステップ
機体を手に入れたら、いよいよフライト準備です。ここでは、購入から初フライトまでの流れを5つのステップで解説します。
ステップ1:機体購入とリモートIDの登録
自分に合ったドローンを選んで購入したら、まずは国土交通省の「DIPS 2.0」で機体登録を行いましょう。登録が完了すると発行される登録記号を、機体に表示(テプラなどで貼付)する必要があります。
ステップ2:飛行計画の通報と許可・承認申請
次に、「いつ」「どこで」「どのように」飛ばすかを決めます。その計画に基づき、必要であればDIPS 2.0で飛行許可・承認申請を行います。また、飛行計画が決まったら、他のドローン操縦者と情報を共有するため、「ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)」で飛行計画の通報を行いましょう。
ステップ3:ドローン保険への加入
万が一の事故に備え、対人・対物の賠償責任保険への加入を強くおすすめします。機体登録の際には保険加入の有無を申告する必要があり、未加入だと飛行させられないケースもあります。年間数千円~で加入できる保険が多いので、必ず検討してください。
※オススメ:SORAPASS care(保険料を含めて年間5,000円(税込))

ステップ4:飛行マニュアルの作成と携行
安全な飛行のため、操縦者の遵守事項や機体の点検手順などを定めた飛行マニュアルを作成し、飛行時には必ず携行しなければなりません。国土交通省が公開している「標準マニュアル」を参考に、自分の機体や飛行内容に合わせてカスタマイズしましょう。
ステップ5:初フライトと安全な操縦練習
すべての準備が整ったら、いよいよ初フライトです。最初は許可のいらない屋内や、四方をネットで囲まれたドローン練習場など、安全な場所で練習しましょう。ホバリング(空中での静止)、前後左右への移動、上昇・下降といった基本的な操縦をマスターすることが、美しい空撮への近道です。
魅力的な空撮映像を撮るテクニック
ドローンの操縦に慣れてきたら、次は映像のクオリティを高めるテクニックを学びましょう。初心者でもすぐに実践できる基本的なコツをご紹介します。
基本的なカメラ設定(解像度・フレームレート)
- 解像度: YouTubeなどで公開するなら4Kがおすすめです。編集でトリミングしても画質が劣化しにくいメリットがあります。
- フレームレート(fps): 1秒間の動画が何枚の静止画で構成されているかを示す数値です。映画のような質感なら24fps、一般的なテレビ放送のような滑らかさなら30fps、スローモーション編集をしたい場合は60fps以上で撮影すると良いでしょう。
覚えておきたい基本のカメラワーク
ただ飛ばすだけでなく、ドローンの動きを意識することで映像は格段にプロっぽくなります。
- ドローニー: 被写体にカメラを向けたまま、ゆっくりと後退しながら上昇していく動き。壮大な景色と被写体を同時に見せたいときに効果的です。
- ロケット: カメラを真下に向けて、真上にゆっくりと上昇する動き。風景の全体像をドラマチックに見せることができます。
- サークル: 被写体を中心に、一定の距離を保ちながら円を描くように旋回する動き。建物や人物などを立体的に見せたいときに使います。
- フォロー: 動いている被写体(人、車、自転車など)を、一定の距離と角度を保ちながら追いかける動き。躍動感のある映像になります。
ゆっくり、滑らかに動かすことが、美しい映像を撮る最大のコツです。初心者には「自動撮影モード(DJIならQuickShots)」を推奨します。
プロが使う構図のテクニック
ドローン空撮でも、写真や映像の基本的な構図が役立ちます。
- 三分割法: 画面を縦横に三分割する線をイメージし、その線が交わる点に被写体を配置する構図。バランスの取れた安定感のある映像になります。
- 日の丸構図: 被写体を画面のど真ん中に配置する構図。シンプルですが、被写体の存在感を強くアピールできます。
- リーディングライン(誘導線): 道路、川、海岸線などを画面に入れることで、視聴者の視線を自然に奥へと導く構図。奥行きと広がりを表現できます。
ドローン撮影にかかる費用の内訳
ドローン撮影を始めるにあたり、どれくらいの費用がかかるのかも気になるところです。ここでは、自分で始める場合とプロに依頼する場合の費用について解説します。
機体購入の初期費用(本体・予備バッテリー)
ドローン撮影を始めるための初期費用は、主に機体本体と関連アクセサリーです。
- ドローン本体: 5万円~20万円
- 予備バッテリー: 1本あたり1万円~2万円
- その他アクセサリー: プロペラガード、NDフィルター、microSDカード、キャリーケースなどで1万円~3万円
初心者が一式揃える場合、合計で8万円~25万円程度を見ておくと良いでしょう。
登録や保険にかかる維持費用
ドローンは購入後も、維持費用がかかります。
- 機体登録料: 申請方法により異なりますが、1機あたり900円~2,400円(3年ごと)
- ドローン保険料: 年間5,000円~30,000円程度
これらは安全にドローンを運用するための必要経費と考えましょう。
プロの撮影会社に依頼した場合の料金相場
自分で撮影する時間がない場合や、より高いクオリティを求める場合は、プロのドローン撮影会社に依頼するのも一つの手です。※Tactics(タクティクス)は柔軟に対応させていただきます。
- 静止画撮影(写真): 5万円~10万円程度(撮影数時間、データ10~20カットなど)
- 動画撮影: 10万円~30万円程度(撮影半日、編集込みのショートムービー作成など)
料金は撮影内容、拘束時間、編集の有無、許可申請の代行などによって大きく変動します。自分で機材を揃えて学ぶコストと、プロに依頼する費用を比較検討してみるのも良いでしょう。
ドローン撮影に関するよくある質問
最後に、ドローン撮影に関して初心者が抱きがちな疑問にお答えします。
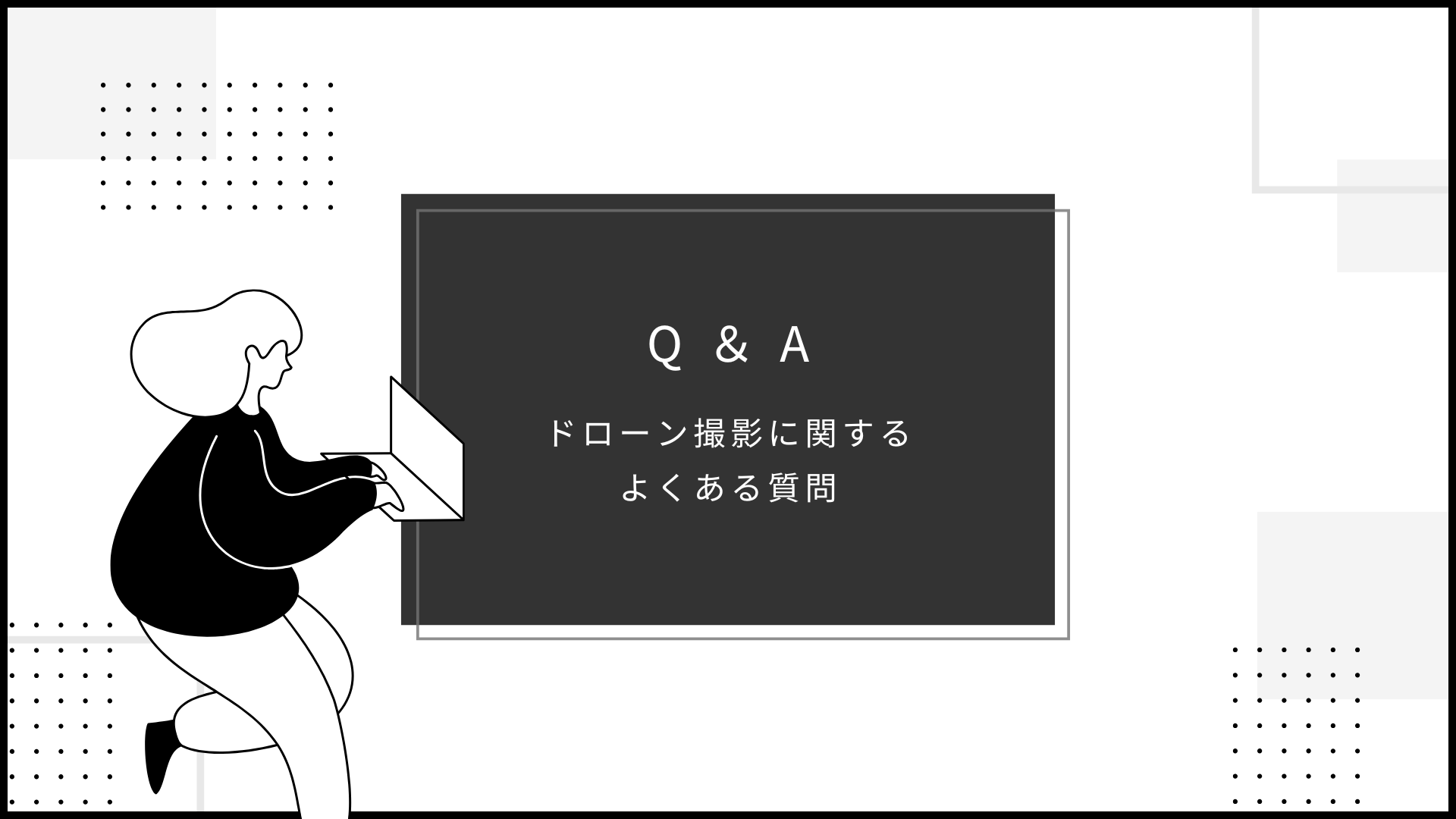
個人での撮影でも許可は必要ですか?
はい、必要になる場合があります。 航空法をはじめとするドローン関連の法律は、撮影者が個人か法人か、目的が趣味か仕事かに関わらず、等しく適用されます。人口集中地区で飛ばす場合や、夜間に飛ばす場合など、定められたルールに該当すれば、個人であっても必ず許可・承認申請が必要です。
特定の場所(河川・公園・海上)で飛ばすには?
航空法とは別に、土地や施設の管理者が定めたルールにも従う必要があります。
- 河川: 河川法に基づき、管轄の河川事務所への確認や届出が必要な場合があります。
- 公園: 多くの都市公園では、条例でドローンの飛行が禁止されています。必ず公園の管理事務所や自治体に確認してください。
- 海上: 海上での飛行は航空法上の規制は少ないですが、漁港や海水浴場など、管理者がいる場合はそのルールに従う必要があります。また、海岸法に関わる場合もあるため、管轄の自治体や土木事務所への確認が安心です。
「航空法をクリアしたからOK」ではなく、必ずその場所の管理者にも確認するという二段構えの意識が大切です。
資格がないと仕事にできませんか?
いいえ、現状では資格がなければ仕事にできないという法律はありません。 クライアントから依頼を受けてドローン撮影を行う場合でも、法律で定められた許可・承認を適切に取得していれば、資格がなくても業務を請け負うことは可能です。
ただし、国家資格を持っていることは、安全な飛行に関する知識と技能を国から証明されている証になります。クライアントからの信頼を得やすくなったり、複雑な案件を受注しやすくなったりするメリットは大きいでしょう。
まとめ
今回は、ドローン撮影を始めるためのルール、機体選び、具体的なステップ、撮影テクニックまでを網羅的に解説しました。
- まずは法律を理解し、100g以上の機体登録と飛行ルールの確認が最優先
- 初心者は「画質」「安定性」「価格」のバランスが取れた5万円~15万円の機体またはレンタルがおすすめ
- 機体購入後は、保険加入、飛行計画の通報、マニュアル携行などの準備を忘れずに
- 最初は許可のいらない安全な場所で、ゆっくり滑らかな操作を練習しよう
ドローン撮影は、ルールが多くて難しそうに感じるかもしれません。しかし、一つひとつのステップを正しく踏んでいけば、誰でも安全に、そして合法的に空撮を楽しむことができます。
この記事が、あなたの素晴らしいドローン撮影ライフの第一歩となれば幸いです。空からの景色をあなたの作品にしてみませんか。

国家資格保有者や経験者を中心に、
ドローン人材と企業をつなぐ求人プラットフォーム
資格後の迷子期間をなくし、最初の案件に挑戦できるサポート
トライくんの詳細を見る ▶実案件を通じて営業力・受注力を鍛えるトレーニングプログラム
Tac10の詳細を見る ▶※実績に基づいた安心サポートを提供しています
